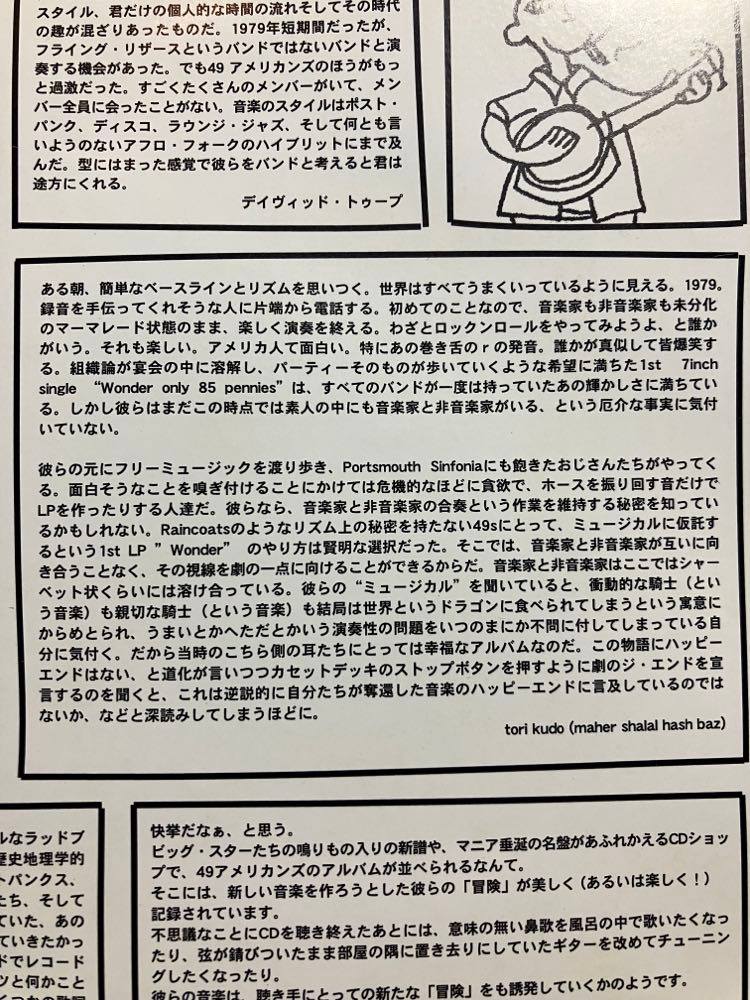the 49 Americans
ある朝、簡単なベースラインとリズムを思いつく。世界はすべてうまくいっているように見える。1979。録音を手伝ってくれそうな人に片っ端から電話する。初めてのことなので、音楽家も非音楽家も未分化のマーマレード状態のまま、楽しく演奏を終える。わざとロックンロールをやってみようよ、と誰かがいう。それも楽しい。アメリカ人て面白い。特にあの巻き舌のrの発音。誰かが真似して皆爆笑する。組織論が宴会の中に溶解し、パーティーそのものが歩いていくような希望に満ちた1st 7inch single “Wonder only 85 pennies” は、すべてのバンドが一度は持っていたあの輝かしさに満ちている。しかし彼らはまだこの時点では素人の中にも音楽家と非音楽家がいる、という厄介な事実に気付いていない。
彼らの元にフリーミュージックを渡り歩き、Portsmouth Ainfoniaにも飽きたおじさんたちがやってくる。面白そうなことを嗅ぎ付けることにかけては危機的なほどに貪欲で、ホースを振り回す音だけでLPを作ったりする人達だ。彼らなら、音楽家と非音楽家の合奏という作業を維持する秘密を知っているかもしれない。Raincoatsのようなリズム上の秘密を持たない49sにとって、ミュージカルに仮託するという1st LP “Wouder” のやり方は賢明な選択だった。そこでは、音楽家と非音楽家が互いに向き合うことなく、その視線を劇の一点に向けることができるからだ。音楽家と非音楽家は ここではシャーベット状くらいにひあ溶け合っている。彼らの””ミュージカル”を聞いていると、衝動的な騎士(という音楽)も親切な騎士(という音楽)も結局は世界というドラゴンに食べられてしまうという寓意にからめとられ、うまいとかへただとかいう演奏性の問題をいつのまにか不問に付してしまっている自分に気付く。だから当時のこちら側の耳たちにとっては幸福なアルバムなのだ。この物語にハッピーエンドはない、と道化が言いつつカセットデッキのストップボタンを押すように劇のジ・エンドを宣言するのを聞くと、これは逆説的に自分たちが奪還した音楽のハッピーエンドに言及しているのではないか、などと深読みしてしまうほどに。